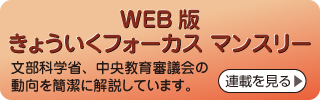Vol.64:日本と中国の架け橋になりたい私 ―異文化交流と多文化共生に向けて―
日本と中国の架け橋になることを夢見る私の心の旅を綴ります。
架け橋の夢を描いた少女は今、大学生になり、京都で日中学生交流団体に所属していろいろな活動をしています。そんな私の今の悩みは、どうやって中国に興味を持つ仲間を増やすかです。
〇架け橋への私の思い
私は長野県上田市で生まれました。両親は中国人です。そのため自分も中国国籍です。生まれてすぐに中国に帰り、中国の遼寧省丹東市で9歳までの8年間を過ごしました。10歳になり日本に戻り、小学校から高校まで日本の公立教育を受けました。今は京都の大学で東アジアの言語・文化・社会を学んでいます。
私が通った市立小学校の学区には外国にルーツがある子どもがたくさんいました。その多くは在日中国人、日系ブラジル人、出稼ぎに来ているベトナム人やインドネシア人の子どもでした。そのため、私の小学校には日本語教室がありました。子どもたちはまずここで日本語を学んでから普通学級に転入します。
日本語教室に在籍する期間は人によって違います。私の場合は全く日本語ができなかったので、約10か月在籍していました。
日本と中国の両方にルーツがある私は、幼い頃から日中関係に関心を持っており、家族全員が日中友好を常に願っておりました。そして少しずつ、自分も日本と中国のために力を尽くしたいという思いが芽生えました。
〇父の言葉と日本語教育
高校生になった私は、少しずつ、架け橋への思いを実行に移していきました。私の思いを後押ししてくれたのは、次の父の言葉です。「社会に貢献する人間になりなさい」。子どもの頃から耳にタコができるくらい言われました。
私の初めの舞台は、故郷である上田市でした。その頃に知ったのですが、上田市にある24の市立小学校のうち、日本語教室がある小学校は2校しかなかったのです。たまたま私の家が日本語教室のある学校の学区の中だったので、私は恵まれた環境で日本語を習得できました。日本語教育は父の言葉とともに、私にとってとても大きな支援でした。
やがて私は、同じ地域に住む日本人と外国にルーツがある市民との交流が、異文化交流と多文化共生を推進するのではないかと考えるようになりました。日本人にとっては外国にルーツがあるお隣さんと仲よくなり、その人を通してその国を知ることは、その国に関心が生まれるきっかけになります。外国にルーツがある人にとってはお隣さんの日本人とつながるきっかけとなり、日本での生活がより深く根づくものになることでしょう。この考えは日本と中国の話に限らず、他の国にとっても共通です。
〇高校生の私
外国にルーツがある市民と日本人市民とが交流を図り、多文化共生社会を目指した料理イベントを開きました。イベント当日は外国にルーツがある市民と日本人がペアになって長野県の郷土料理であるおやきを一緒に作りました。ペアになることで交流が進み、また郷土料理を作ることによって外国にルーツがある市民は、自分の住んでいる地域への理解がより深まりました。日本人の中には、外国にルーツがある人と初めて話す人もおり、会話が盛り上がりました。また、このイベントは国籍の制限を設けなかったので中国の方だけではなく、タイや香港の方も参加してくださいました。
在日外国人は2023年末で約341万と過去最高を更新しました。国別にみると中国がいちばん多く約82万人、続いてベトナム約56万人、韓国約41万人、フィリピン約32万人、ブラジル約21万人、ネパール約17万人、インドネシア約14万人、ミャンマー約8万人です。私の故郷である上田市は人口約15万人に対して約3%の約5000人が外国にルーツがある市民です。
彼らは全員が地域の日本人とよい関係性を築けているわけではありません。文化や生活習慣の違いでトラブルや問題も起きています。また、同じ国の出身者同士のコミュニティもあるため、日本人との交流があまり進まないケースもあります。同じく日本人のほうも、近くに外国人が住んでいても必ずしも関わりがあるわけではないのです。
ところで、私が「外国人」という表記を使わずに、「外国にルーツがある」という表記にこだわるのは、日本に住んでいる外国の人々を単純に「外国人」と表現できないほど、人によって複雑な事情があるからです。例えば外国籍から帰化した日本人や複数のルーツを持つ人、両親は外国人だけど日本で生まれ育った人などがいます。自分のルーツが日本にだけではなく、他の国にもあることが大切です。 しかし、外国にルーツがある人も地域住民の一人として日本人と対等な関係です。日本社会がさまざまな人の対等な関係を受け入れて、多文化共生社会になることを願っています。
〇大学生の私
大学では若者の日中交流にフォーカスし、日中学生交流団体freebird関西支部で活動しています。私は大学で東アジア研究学域に所属しているので、周りの日本人の友人たちは中国にルーツがないにもかかわらず、何かしらがきっかけで中国に興味を持った人が多く、入学当初はそれに驚きました。
高校までは故郷の上田市にいたのですが、中国に興味を持っている同級生は数えるほどしかいませんでした。多くの人は韓国や欧米圏の国々に興味を持っていました。そのため高校生の私は、中国に興味がある若者は本当に少ないんだなと思っていました。
しかし、京都では、自分が思った以上に中国に興味がある日本の若者が多くいることに気づき、日中間の青年交流は成り立つと思いました。その後、freebirdに出会い、その理念に共感したので役員に応募しました。
日中学生交流団体freebirdは2005年に上海で設立された学生団体で、活動理念は「日中学生の相互理解の場を創出する」です。今は関東・関西・北京・上海の4つの支部に分かれて活動しています。私は関西支部に所属しており、語学交流部という言語にまつわるイベントを企画運営する部署でリーダーを担っています。関西支部は4つの支部の中でもいちばん規模が大きく、近畿圏の各大学の学生で日本人学生と中国人学生のそれぞれ約25人ずつで構成されています。
私たちが運営するイベントは、料理から伝統衣装、言語交換会などさまざまなものがあります。私たちはあくまでイベントを企画運営する役員なので、どのイベントも役員の身内の者だけではなく、SNSなどで積極的に宣伝し、一般参加の大学生を募っています。
いちばん印象深かったのは、日本の学生を中国旅行に連れていく企画「青春ロマン学生訪中団」です。参加した日本人の学生が口をそろえて「実際に中国に行けてよかった」と言います。実際に行くことは得がたい体験です。実際に現地で過ごし、中国のよいと思った点も、自分に合わないなと思った点も、中国への関心を高めてくれるきっかけになります。
学生団体なので社会人になったら続けることはできませんが、大学を卒業するまで力を尽くし、理念である「日中学生の相互理解の場を創出する」ことを実現できるようにがんばりたいです。また、日中の若者がこれからも交流を保ち、増えていくことを願います。
〇この先の夢 ―理想の日中関係
私の理想はお互いの国に対して興味関心を持っている人が増え、旅行や留学で実際に相手の国に行く人が増えることです。日本も中国も相手国の不確実な報道が原因で、第一印象がよくなくなることが多いです。一度ネガティブな印象を持ってしまうと、現地を直接訪れるきっかけがなければ相手国のよいところはなかなか見つけられません。
最近日本人の中国での短期滞在がビザなしになったというすごくうれしいニュースがありました。これをきっかけに今までより多くの日本人が実際に中国を訪れ、自分の目で中国を見て体験する人が増えたらいいなと思います。 また、中国人は以前から日本への関心が高く、2023年の中国人留学生の数は約11万人、訪日中国人観光客は約242万人でした。旅行、留学、駐在など一般の人が相手国に訪れることと民間の交流がさらに盛んになることがよい日中関係を作ると思います。
〇私の悩み ―解決したいこと
今までの活動を通して感じていることは、興味がない人に興味を持ってもらうのはとても大変だということです。何かのことについてもっと多くの人に興味を持ってほしいとがんばって広めている人は、どうやったら広められるのか、どうやったら興味を持ってもらえるのかと、必ず考えて悩むでしょう。
正解は一通りではないのでいろいろ試ししてみることが大切だと思います。幸い、この稿を目にする人は多いと思います。よいご助言をいただけることを期待しています。
〇最後に ―父の言葉をもう一度考える
父の「社会に貢献する人間になりなさい」という言葉はすごく重く、考えさせられます。何をもって社会に貢献したといえるのか、そもそも納税やごみの分別など、社会は、人々が深く考えずとも社会に貢献するようなシステムをなしています。私も毎日「社会に貢献するぞ」という意識を持っているかといわれたら、そうでもないかもしれません。
しかし、「こういう社会がいいな、そのためにこういうことをしてみよう」と思って行動する人が少しでも増えると、社会はよりよくなるのではないかと思います。そのために、これからも力を尽くしていきたいと思います。
(立命館大学文学部東アジア研究学域現代東アジア言語文化専攻 張驪驕)