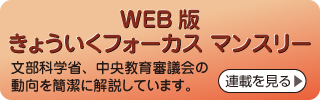Vol.68:古くて新しい本
すばらしい本なのに、出版社に在庫のない本を古書店で見つけました。
浅井清&黒井千次監修「読んでおきたい日本の名作」(教育出版)のシリーズ39冊のうちの3冊です。大きな文字とやさしい表記で、親切な脚注までついていて、名作を楽しむことができます。
古書店や図書館で見つけたら、ぜひ読んでみてください。
◆<その1>『夏目漱石Ⅰ 現代日本の開花 ほか』教育出版
「現代日本の開花」は、明治44年8月に和歌山で講演した内容を逐語記録でまとめたものです。ゆっくり味わいながら読むと、講演をじかに聞いているような気になってくるから不思議です。
「私の個人主義」は、大正3年11月25日に学習院輔仁会(現在の学習院祭)の講演の内容をまとめたものです。落語の「目黒の秋刀魚」の話や、漱石が学習院の教師になりたかった話が挟まっていますが、芸術の話が中心です。
「中味と形式」は、明治44年8月の堺での講演内容をまとめたものです。中味と形式について、さまざまな事例をもとに漱石流の見解を語っていて、現代の私たちの物の見方にもヒントを与えてくれます。
「模倣と独立」は、大正2年12月12日に第一高等学校(現在の東京大学教養学部)での講演内容を紹介しています。人間は模倣傾向と独立傾向を持っていますが、独立傾向を大事にしたほうがよいと学生に説いています。
巻末に、石井和夫「解説」「略年譜」と、清水良典のエッセイ「ロンドンの孤独と憂鬱」が収録されています。
◆<その2>『柳田国男 毎日の言葉』教育出版
日常(昭和31年前後)使われる言葉の意味を、柳田流に解釈し解説したものです。
「毎日の言葉」(「アリガトウ」「タベルとクウ」「モシモシ」「よいアンバイに」など24語)、「買い物言葉」「あいさつの言葉」「どうもありがとう」「女の名」「ウバも敬語」「御方の推移」「上臈」「人の名前に様を付けること」「ボクとワタシ」で構成されています。
柳田国男は、日本における民俗学の創始者であり、研究する民俗と同様に言語は重要なものとしています。「なるほど」「そうだったのか」と世界を広げてくれる内容です。
巻末に、沢木幹栄「解説」「略年譜」と、川崎洋のエッセイ「ウソとイツワリ」が収録されています。
◆<その3>『森鴎外Ⅰ 最後の一句・山椒大夫 ほか』教育出版
「最後の一句」「寒山拾得」「山椒大夫」「高瀬舟」「阿部一族」で構成されています。
小学校高学年、中学校や高校の国語の時間に学習したので、あらすじはわかっていましたが、じっくり読み返してみると、「こういいことだったのか」「ここには感動した」という新しい発見があって、充実した時間を過ごすことができました。
森鴎外の他の作品も読みたくなった次第です。
巻末に、大塚美保の「解説」「略年譜」と、中沢けいのエッセイ「森鷗外の固さと静けさと豊饒さ」が収録されています。
(教育調査研究所研究部長 小島 宏)