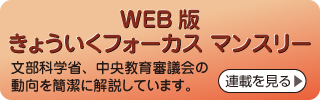Vol.70:(提言)「教育」をもう一歩「厳密に」考えてみよう! ―今次学習指導要領の改訂に際して―
はじめに
本稿は、私が教育学者の一人として、少数派とはいえ考えてきたことを、今次の学習指導要領2030年改訂に際して明記しておこうと考え、ここに要約的にまとめてみたものである。
世界の教育界は、現在主にOECD/PISAの成績とその順位によりその良し悪しが測られているが、私はその意義とともに、「外部専門家external expert」の一人として疑問も抱いてきた。
ここにその理由を述べつつ、改めて「教育」固有の意義を考えてみたい。とうてい哲学界の水準には及ばないが、部分的にせよ、E.フッサール流に「『厳密な学』としての『教育学』を考えてみよう」ということである。この試みが後輩の研究者・実践家の参考になるか否かは読者に任せるとして、この意図だけは了としていただきたい。
1 人を「教育」するとはどういうことだろうか?=「教育」再考
(1) 「広義」の「教育」
「教育」は「自分の生き方や考え方等において、他人に何らかの影響を与えることを意図する行為・営み」と私は考え、多くの人もほぼそう考えていると思ってきた。この点については、なぜか多くの教育学者・教育関係者はほとんど重要な問題を含むものとしない。
教育学では「教育の目的」面から「事実の教育(大人にすること)」(教育社会学)と「理想の教育(全人形成・全面発達等)」(教育思想・哲学)とを分けたうえで、前者を後者に向けて営むための学問の総称と考えてきた。
通常話題になる「教育」は、学校などの「教育」を中心に「養育・養護・保育・しつけ・訓練・鍛錬・知育・徳育・体育・教化・洗脳・宣伝・指導・助言など」と別称された行為を広く含む総称、「人がそう呼んでいる教育一般」である、と言ってよい。
中でも最近は、「教育」の目的が、日本では「人材(財)養成」であるという声のほうがはるかに大きい。もしそうなら、一体「誰(何)のため」に教育するのだろうか。本来ならば「その人、その子ども個々人のため」でなければならない。ところが「人材」というからには「社会や国に役に立つ材料としての人」がイメージされるのであり、現行の学習指導要領のように「社会に開かれた=社会に必ず役立つ」人づくり、という理解が一般化している。
目前のその子個人、子どもたちのためではない。PISA/2030ではAgencyに焦点化し、学習指導要領改訂作業も「個別最適化」と言い、個々の子どものために行っているとされるが、全体を俯瞰して見たらどうか?
当初の私は、TIMSSやPISAがよい例であるが、自由民主主義国も権威主義国(旧社会主義国が多い)も区別なく、経済的観点からの教育への関心に偏していることに問題を感じていたが、その点は既にかなり改善された。しかし、依然として疑問はなくなっていない。
なぜなら、両調査とも、その政治社会体制の如何を問わず、国民の資質・能力の一部、それが読解力、数学、理科に限定されていながら、それが各国の「教育水準全体」を示すかのように、信頼できる数値や序列とされてきたからである。しかしWell-beingは「個人の尊厳」という政治的要素を抜きに考えられるだろうか?
もう一つ、世界は今やVUCAの時代だとして、ますます不安定な時代にならざるをえないことが強調されている。しかし、果たして「無責任に」そう言って受け身的に、うまくその波を乗り越えていく「資質・能力」を育てればすむのだろうか。VUCAを言いすぎて、本来、安定させておくべき倫理・原則まで、利害・損得によって不当にずらしたり、灰色の部分を拡大解釈したり、原点・中心をぼかして隠した部分を作ったりして、周囲の反応を試してはいないか。
しかし、本当にVUCAの時代だからとして、何もかも不確かで不安定なままの社会が続くだろうか。誰も信じられない社会、というものが成り立たないことは明らかである。そこに集団はあるが社会はない、群れはあるが組織はない。社会は「秩序」ある組織をもっている。「秩序」あるいは「法(律・令)」(公的な約束事・決まり等)をもつのが社会である。それが揺らげば社会は壊れて群れに変質していく。
悪い場合は、法を人間の上に置く本来の順序が逆になり、人間が秩序や法を人間の都合のよい道具とする、それらへの軽視・無視が起こり、言い返してごまかすようになり、だましたり、子どもじみた屁理屈を言って、言い逃れをしたりするのが当たり前のこととなる。
結果としてその社会は乱れていき、ついには互いの約束が信用できなくなって社会は瓦解する。
そんな時代の「教育」というものを考えてみよう。いかにも難しいことだということがすぐわかる。激動を乗り切る資質・能力をもってさえいればよいのだろうか。現在の日本人等を見ていると、20代以上の多くの人は、将来に不安があっても今がよければいいか、という刹那主義に我を忘れているように見える。
結果的には自分の不安が増すばかりであり、子どもの教育を十分考える余裕もいっそうなくなる。私の子ども時代ほど、子どもは子ども自身として、個人の人間的尊厳をもつ大切な存在とされてはいない。
(2) 「狭義」の「教育」
一方、現在の教育学界・教育界には、「教育」という用語に固有の意味をもたせようとする動きはない。だが、自然界を見ても法律等を見ても、「教育」を上述のような総称ではなく、より厳密に、それらとは異なる固有の意味があるものと考え、民法等では「養育」と明確に区別をしている。そういう区別を前提にして、本来の「教育」の定義を狭義化しようと試みた。
《「教育」とは「子どもの未来決定の自由」(の権利)を認めるもの=「自立independence」の保障:全ての人(子ども)の人格と能力を峻別し、能力は人格の一部と見てその人格の存在価値を平等なものとし、個性、意志、志望、進路等における自由(多様性)を認め、「国の未来の主権者」の基本的人権等(生命、思想、職業等)を承認し、自立(独立)(特に精神的自立)を実現する事実・行為・過程。ただし、自立は依存をなくすことではなく、依存の対象・数・関係を変えること。》
その趣旨は、特に近現代の人間の場合、子どもたちは大人や親の政治的・経済的要請に従属し、強制されるロボットや人形ではない。自身の個性、意志、志望等の自由をもつものであり、自立した後に、どういう人材になるのか、思想的に右に行くのか左に行くのかは、本人が決められることに独自性がある。
この意味で、1979年の私の処女作以来、子どもには「未来決定の自由」があると私の言葉で主張してきた。しかも子どもは「国の未来の主権者」であるから、それにふさわしい政治的教養を平等に育てられる必要がある。最近は、世界も日本も保守系右派の政治家が活発であり、ジャーナリズムもSNSも、若い層がそれを歓迎する傾向が見える。世界の今の政治指導者は、「国のための公教育」(国家主義・権威主義)を強調して人の生命を、戦争等で兵士や戦争用具として実に軽く見ており、お金で買えるモノとして、家畜かロボット、あるいは使い捨ての消耗品のように扱っている。こういう人間感覚が子どもに育っていくと容易ならぬ事態になると思う。
「所与性」および「所奪性」への畏敬(関根清三)が前提として大切である。我々の存在は、現在既に与えられている全宇宙のもつ力(エネルギー)により生み出され、支えられている価値あるものであり、もしこの宇宙がなかったら我々は存在しえない、一人一人かけがえのない個性的生命である。新しい倫理(学)へ向かってその確立に注力せねばならない。
特に「個性的自立」を尊重しない多様性の最近の強調は、国家主義・排斥主義的な右翼化への、日本人の同調志向の裏返しの動きとして警戒すべきである。新時代の倫理(学)が求められるのに、古いものへ回帰させるかのようである。日本ファーストを高唱する人々、特に政治家は自分が「利己主義者」に等しいことを恥じないのか?
3 一般社会が「教育」と呼んでいるのは何を指しているのか?
「教育education」は「教化indoctrination」とは異なり、本人が何になるかの自由を認めるものとの考え(初代東大教育学部長 海後宗臣)に改めて注目すべきである。
現状は、この区別が学者間でもなく、中国や北朝鮮の「教化・洗脳」も自由主義国の「教育」も国際調査などで同一視されているが妥当だろうか。私たちは研究者なのだから、より厳密に考える責任がある。
全ての動物の「教育」が「自立(独立)independence」を目指している事実に注意すべきである。「自立」を普通名詞ではなく「教育学固有の名詞=学術用語」として扱う必要がある。この「教育」の固有性を認めるならば、次の2点についての明確な区別が必要である。
(1) 私教育と公教育
一般に、人間の場合、まず「教育」の場面として描かれるのは乳幼児期の子どもの養育の姿である。「家庭教育」とか「(乳)幼児教育」と呼ばれるのがそれである。これは親ないし保護者である個々人とその家庭によって質・量ともに異なる。しかも、それは私事(わたくしごと)であり、親や保護者の自由になる。これを「私教育」と呼ぶ所以である。
したがって、ジャーナリズムも公に報じることはまれなので、報じられる「教育」記事は通常みな「私教育」を指すことはない。
加えて現在熟考すべきは、親や保護者が子どもを通わせたり自らも学ぶ、公権力から独立した種々の教育産業がある。かつて受験予備校などを一括して「産業」として批判した私は、その中に「本当の教育」を求めて個人的・集団的な「学習塾・〇〇教室・企業内教育・フリースクール等」も見いだせること、その果たしている独自の役割も、特にNPOなどの団体を作って活動している人々の「教育」に、今後の「義務教育」以後の個別の、個性を伸ばす教育に大きな可能性を感じた。
他方、それでは社会生活上、国民・市民として、必要な意思疎通を行うことができない。そのために必要な教育の部分は、誰にでも平等に、共通に必要な能力を、同一水準にまで身につけさせることができなければならない。その点で、差別や格差は原則としてあってはならない。そこで「公権力」が親の私教育の一部を割いて、強制力を働かせてでも子どもたちに民主主義的な(ぺスタロッチ、J.デユーイ)、「国民として必要最低限の共通教養を育てる教育」を行う。通常これは「普通教育」と言われる。
だが、これは「公権力の質」により間単に「教化」に変質する。その例が一部の旧社会主義国である。さらには「個々の子どもの個性を可能な限り伸ばす」教育の機会を与えなければならない。特に日本近代の教育制度の場合、欠けていたのが子どもたちを「国の未来の自立した主権者」として育て上げることであった。
OECD/2030も「責任ある当事者意識Agency」を強調したことに留意すべきである。日本人は「主権者意識のない国民」として個々人が「責任」をとろうとしないから、政治家に横取りされて「無責任体制」が生まれ、現在も極右政治家が天皇制を利用して「公教育」支配をねらっている。(白井 聡)
しかし、私教育も「教育」である限り、公教育との区別とともに、連携をも図るべきである。「主権者教育」は、本来全ての人に平等な「公教育」がその責任をもつべきだが、政財界は常に「(思想)教化」のために「公教育」を支配しようとする。 それを防ぐには、公教育の典型たる「義務教育」は、「国民の共通基礎教育」(だいたい、最低小4までの読・書・算+基礎的社会規範・国民意識)のみでよく、「個性を伸ばす教育」が、それ以外の公・私の教育で共に展開されるとよい。
こういう主張は必ず親の「経済上の格差(拡大)問題」が考慮されていないと批判されてきたが、学力格差や体験格差の何もかもが「経済格差」に還元されるわけではなく、保護者の自覚や当事者意識による場合も多い。経済上の困難を抱えている子どもに手当は必要だが、全ての子どもを金太郎飴のように等質にすることは「教化・洗脳・訓練」ではあっても「教育」ではない。
いかにして保護者や親、行政から軽視され、放置されてきた「私教育」の重要性を、それらの人に認識させるかが鍵であり、今後の工夫の最大の困難点であるが、それにはまず、利益優先の産業主義から脱却し日常生活の価値の転換を図る必要がある。(養老孟司・今井悠介)
(2) 学校教育と学校外教育(生涯教育と社会教育)
公教育の典型は学校教育であるが、その「学校」が保護者や親から徐々に見放されつつある。「不登校」児童生徒の高止まりや増大、代替学校(オールタナティヴ・スクール)の公認と増加、「いじめ」件数の増加、高学歴社会化の進行による受験教育の全面展開と学校教育からの逃避の両極化、学校外の自己学習の場・機会の増大、学校の内外でのITやAIによるデジタル化の連携の場の拡大、デジタル学習システム・機器の普及による通信制・単位制の遠隔教育の拡充、生涯学習・リカレント教育の必要性の増大など、現在の科学技術は学校の内と外を分ける意味を失わせつつある。世界中でコロナ禍がこの傾向を強めた。
高校以後の大学・大学院が、義務教育修了者なら、いつでも、どこからでも、何年かけてでも入退学のできる生涯学習・社会教育機関になるならば、時代は変化の度合いを強め、常に新たなイノベーションを求めて、その種の「人材」(16歳以後は大人とみなし、主体として自らに適した材料となる意志と責任をもてるのでOK)を学校の内外に行き来させ、自らの質を向上させて、自分も社会も共に満足を得られると考える。
もしそうならない場合は、16歳以後の大人として自己責任で社会のための材料となることを優先することは承認する。
学歴社会は既に硬直化し、もはや高学歴がものをいう社会ではなく、その後の人生でまさにどこまで自由で独創的に、国や地域を越えて物事を考える力をもつか、の時代に入っているのではないか。問題解決や課題達成のための道具としては質のよいものをもたねばならないが、ソレは必ずしも多くない。当面リテラシー中心の義務教育をしっかり行えば、デジタル化社会にも特に心配はない。現に日本の場合は遅れ気味だが大きな教育問題を生んでいない。
おわりに―条件整備問題の格上げ
今回の学習指導要領の改訂にあたっては、従来は答申の最後に行政側に向けた条件整備の問題等についての章ないし節を付したが、今回は学習指導要領の改訂内容の答申と同じレベル、重要さを示す答申のもう一つの柱として格上げされるという。これは大いに結構だと思う。問題はそれが尊重され、具体化する方向に政府全体を動かせるかどうかである。
元来、教育行政は教育の外的事項、ほぼ条件整備にあたる部分が主たる担当部分であった。いわゆる「教育の政治的・宗教的中立性」の問題に関わる、今に続く論争部分であり、従来は完全な中立性は存在しない、というのがほぼ定説であったが、私は「不完全でも可能な限り中立的であるべきだ」との原則を貫くよう主張してきた。
そして、ここ20年ほどは、その根拠として、これまで誰も言わなかった「子どもの未来決定の自由=自立」(の権利)を侵すことになるからだ、と明言するようにしてきた。
最後に、要約的に教員問題とデジタル機器の活用についてのみ取り上げる。前者は量が喫緊の課題になっているが、質も決して無視できない。古来言われてきたように、よい教員が得られるかが最重要である。後者については、教員も子どもも「自己研修」「自学自習・自己教育」用に使用すべきである。一日も早く、まず使用倫理を暫定的にでも決めるべきである。
(名古屋大学名誉教授 安彦 忠彦)