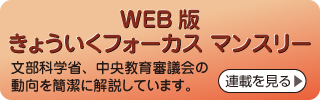Vol.69:探究の内実化を可能にするエコシステム
1.白井俊氏が指摘する「探究」を進めるうえでの「エコシステム」
「エコシステム」とは、ecological system(生態系)の簡略形で、「ある環境の下に生息する生物群集の相互作用」をシステムとして捉える概念である。しかし、近年、拡大解釈が進み、人文・社会的な領域においても、ある状況の下での様々な主体の相互作用に対してよく使われるようになっている。
白井俊氏は、『世界の教育はどこへ向かうか』(中公新書、2025年2月)の中で、「探究を進めていくためには、学習指導要領を変えるだけでは全く十分ではないということである。学校現場の忙しさや、大学の教員養成課程、あるいは入試システムなど、エコシステム全体まで含めて考えなければ、本当の意味での『探究』の実現は難しい」(p.153)と述べている。
白井氏が例示した①学習指導要領、②学校現場の忙しさ、③大学の教員養成課程、④入試システム、以外にも、エコシステムとしての重要な要素は多数存在する。しかし、この4つは間違いなく重要な要素なので、この4つについて考えていく。ただその前に、「ある状況の下」に相当する主要な事柄を簡単に確認しておく。
第1にあげるべきことは、生態的・社会的な持続可能性の問題であろう。ウクライナに対するロシアの侵攻、パレスチナのガザ地区へのイスラエルの攻撃、それにトランプ関税による国際分業システムの綻びが加わり、世界はますます見通しづらい状況となっている。しかし、人類の存続に関わるだけに、持続可能な社会の構築が、喫緊かつ最重要課題であることは間違いない。
2番目は、少子高齢化である。これまでは日本だけに顕著な問題であったが、韓国や中国、そして東南アジア諸国にも拡大してきている。日本の地域社会では、人口減少に伴う活力の低下やインフラの劣化など、対応の困難な課題が山積している。少子化によって、各地域は学校の統廃合という難題にも直面している。
他方で、元気いっぱいのお年寄りが増加しており、今後、学校教育に対する高齢者の貢献は大いに期待できる。ただし、高齢者の参画する仕組みづくりは、実際には容易ではなく大変な苦労が予想される。
3番目は、情報化の進展である。情報機器抜きの世界はもはや想像できない。情報機器が時間のかかる複雑な作業を容易にしてくれている。
その反面で、人間の仕事が奪われるという問題や、高校生や育児世代を中心とする「スマホ依存」の弊害、自然との触れ合う時間の激減、生成AI依存による脳劣化等々、マイナス面も大きい。
4番目は、「教室の中にある多様性」である。「発達障害の可能性のある子ども」「不登校・不登校傾向にある子ども」の比率は上昇を続け、とどまる気配がない。事態への対応は、ある程度進められているが、原因を究明してこの趨勢を断ち切ろうとする動きは低調である。 石井英真氏は、「通常学級の特別支援学級化」という言葉を使っているが、筆者の知人の小学校教員も「三十数名のクラスの中に、15名ほど課題を抱えた子どもがいると、一人の担任教員で対応するのはとうてい無理!」と語っていた。
5番目は日本の青少年の意識についてで、二つに分かれる。その一つは社会参画意識の低さ、もう一つが危機意識の低さ、というか「諦めムード」である。
前者については、白井氏も本著で日本財団による「18歳意識調査」第20回-社会や国に対する意識調査―を取り上げている(p.79)ので、ここでは後者について述べる。
2015年に世界中で開催された「世界市民会議」というイベントのアンケートで、「あなたは、気候変動の影響をどれくらい心配していますか?」という問に対し、「とても心配している」と答えた比率が世界平均では79%であったが、日本では44%にとどまった。そして、「気候変動が引き起こす問題に関心ある?」との問いに対して、若年層ほど関心度が低いという結果であった。少なくともこの十数年、学校教育を通して気候変動問題に対する知識は若年層ほど浸透しているはず、なのにである。
同じ傾向は、国政選挙における若年層の30%前後という低投票率にも見られる。若年層の脱政治意識というべきか、「何をしても変わらない」という諦めムードの蔓延というべきか、日本の学生たちと接していると、他の国々の若年層との大きな違いを感じさせられる。
このような若者の意識形成にこれまでの日本の学校教育の在り方が関わっていることも確かであろう。
2.学習指導要領と探究
「探究」に関わるエコシステムとして、学習指導要領のもつ重要性は、改めて確認する必要もないであろう。「探究」を強調した高校の学習指導要領改訂によって、各教科の教科書も指導書も、そして何よりも高校における授業の進め方が大きく変わってきている。
白井氏の指摘するように、「学習指導要領を変えるだけでは全く十分ではない」。とはいえ、学習指導要領を変えなければ、「探究」を普及させることは難しい。それでは「探究」をさらにいっそう浸透させるには、学習指導要領をどうすればよいのであろうか。
2024年12月の文科大臣の諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」に記載された文言から考えてみたい。
主な審議事項として「質の高い探究的な学びを実現するための『総合的な学習(探究)の時間』の改善の在り方」が上がっている。そのほかに「探究」に対して影響を及ぼしそうな事項として、「柔軟な教育課程編成の促進」「主体的に社会参画するための教育」が目にとまる。 諮問の「顕在化している課題」の欄では「②学習指導要領の理念や趣旨の浸透は道半ば」という項目を立てている。「依然として課題」が残っており、現行の学習指導要領の浸透が不十分なので、その実質化に眼目をおいた表現となっている。残念ながら未来志向という印象は希薄である。
そういった中で、多少とも期待したいのが、前回の最後でも触れた「柔軟な教育課程編成の促進」である。各学校が主体的に独自の教育課程づくりに着手したり、教育委員会が積極的に働きかける流れが生じたりすれば、「探究の内実化」の進展も期待できる。
ただ、現在の学校は、次に述べるような多忙状態で、主体的な対応を期待しにくい状況にある。
具体的に「何をどのように変えていかねばならないか」が学習指導要領に明確に書き込まれなければ、各学校での動きや教育委員会からの積極的な働きかけも生じそうにない。
3.「学校現場の忙しさ」と探究
白井氏が、「探究」をめぐるエコシステムの要素として、学習指導要領の次に例示したのが「学校現場の忙しさ」である。
日本の一般的な労働者の勤務時間はこの半世紀で大幅に短縮されてきたが、教員については1966年から2006年の間に平均残業時間が月8時間から26時間に増加した。この数年、中学校の部活動指導が学校から地域に移行されるなど、「働き方改革」が徐々に進んできたが、「長時間労働の解消」にはほど遠い。
2021年の中教審答申「令和の日本型学校教育」も、「教師の長時間勤務による疲弊や教員採用倍率の低下、教師不足の深刻化」を課題としてあげている。しかし、その対応策として示されているもの多くがICT環境の整備である。しかし、現実の「学校現場の忙しさ」の解消に、ICT環境の整備が有効かつ適切かという点で筆者は懐疑的である。
授業の多くをロボットなどのICT機器に肩代わりさせれば、「学校現場の忙しさ」の解消につながる。しかし、「令和の日本型学校教育」答申が目標としている「一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、……」という姿とは相容れない。
「学校現場の忙しさ」の解消には、答申の示唆する「学校だけではなく地域住民等と連携・協働し、学校と地域が相互にパートナーとして、一体となって子供たちの成長を支えていく」体制づくりが有効であろう。答申では、より具体的に「保護者やPTA、地域住民、児童相談所等の福祉機関、NPO、地域スポーツクラブ、図書館・公民館等の社会教育施設など地域の関係機関と学校との連携・協働を進め」ることを促している。
ただし、これに類する指摘は、決して新しいものではない。2015年12月の中教審答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」では、「学校と地域の連携・協働による社会総掛かりでの教育の実現」が求められていると訴えている。
2022年6月に閣議決定された「Society 5.0の実現に向けた 教育・人材育成に関する政策パッケージ」では、これからの学校教育の在り方として、「分野や機能ごとの多層構造・協働体制・様々なリソースを活用」を提唱している。この構想では、様々なリソースとして「大学、高専、企業、NPO、研究機関、福祉機関、行政、発達支援の専門家等」が想定されている。
保護者や地域住民を重視するか、様々な分野の専門家を重視するかの違いはあるが、共通するのは、学外者の役割を、従来の「支援者」から一歩進めて、学校の教職員が果たしてきた役割の一翼を担う「協働者」のイメージである。
学外の「協働者」が増えると、教員が果たしてきた役割も徐々に変化する。教科等を教えるインストラクターとしての役割以上に、学外者の「協働者」との様々な連携を図るコーディネーターとしての役割が重要になってくる。
4.教員養成制度の在り方と探究
1947年に6・3・3制の新しい学校教育制度が誕生してから、間もなく80年になる。その間に学校教育には多くの新たな教育課題が押し寄せてきた。1960年代には工業化の歪な発展がもたらした公害が社会問題となる中で、公害教育の必要性が叫ばれ、その後、自然保護教育と合流し、環境教育として学校教育に定着していった。
また、20世紀後半を通じて、ヒト・モノ・カネの国境を越えた交流が急拡大する中で、国際理解教育や外国語教育の強化が求められた。その一方で、従来の教科等についても、児童生徒が習得すべき基礎基本と捉えているため、結果的に「足し算」となっていった。
20世紀の末には、主体的・協働的に学ぶ「総合学習」が世界的に広がりはじめ、日本でも1998年の学習指導要領改訂で「総合的な学習の時間」が導入された。「総合的な学習の時間」の趣旨に沿った主体的・協働的な問題解決型の学びに取り組んでいる学校ほど学力テストで好成績だったことから、学習者中心の学びへの転換がなされた。2014年に「アクティブ・ラーニング」が4回も登場する諮問がなされ、「主体的・対話的で深い学び」を強調した現行の学習指導要領にいたっている。
しかし、このような教育課題の増加、教育方法の大きな変化にもかかわらず、1947年に成立した日本の教員養成制度の根幹は、今日もなおほとんど変わっていない。
初等教員免許と中等教員免許の分離、中高の教科別免許制度、教科に関する科目と教職に関する科目の2本柱、都道府県(+政令指定都市)ごとの教員採用試験、教員採用試験合格者の卒業直後からの授業担当等々は1947年当時のままである。学習指導要領の改訂にあわせて、教員免許法等の改訂に踏み込むことはなかったからである。
しかし、今回の2024年12月の「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」の諮問では、同時に、「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」という諮問がなされている。
この「質の高い教職員集団形成」諮問には、「より多くの学生が教員免許取得を目指す教員免許制度の在り方」「教職課程を履修しなかった人が大学院で教員免許の取得が可能な仕組みの構築」「企業等に在籍しながら教師として勤務する際の任用形態の在り方」など、教員養成制度の在り方を大きく変える可能性をもつものが含まれている。学校での授業に参画するうえでの教員免許というハードルを低くして、多様な学外者が学校の「協働者」になれるようにしたい、という文科省の意図が伺われる。
それでは多くの学外者が学校教育の協働者として参画するようになったとき、既存の教員の役割はどうなるのであろうか。諮問文では「教師に求められる役割は、子供たちの主体的な学びへの効果的な支援・伴走へと転換していきます」と述べている。前述の教師のコーディネーターとしての役割とともに、この「支援・伴走」という役割への転換は、「探究」活動の活性化にもプラスに作用するであろう。
5.入試システムと探究
「入試システム」は、現時点では「探究」の浸透の足枷になっている。「探究」中心の出題と公平な評価は至難だからである。しかし、今後、「入試システム」の土台である大学の在り方が急速に変化していく可能性がある。その変化をもたらす主役は、「少子化」と「情報化の進展」である。
現在、18歳人口はほぼ100万人であるが、出生数の減少傾向を考えると、2050年には60万人を割り込むと見込まれる。すでに多くの大学の応募者が定員割れとなっており、志願者はほぼ全員入学できるというのが現状である。
入試を経て入学する学生の割合も減少の一途を辿っており、多様な推薦入学制度で入学する学生の割合が増加している。明らかに大学入試の重みは減少している。
少子化以上に大学の姿を変えるのが、情報化の進展である。コロナウイルスの感染拡大以降、各大学ではオンライン授業のためにICT環境の整備が進み、一挙に情報化が進展した。対面での授業が不可欠な領域もあるが、学生が常に大学のキャンパスに通ってくる必然性は大幅に減少している。N校のような通信制高校が広がりを見せているが、それが大学に拡大していく可能性は大きい。
特に、経済的な停滞の中で、子女が自宅から通える場所で高等教育を受けさせたいと考える家庭は、今後増えていくはずである。現在、私立大学の首都圏集中が著しいが、2050年にもその状態が続いているとは考えにくい。
それでは、2050年における日本の高等教育はどのような姿になっているのであろうか。
2022年度に大学設置基準が改正され、大学に必要とされる施設等の要件が大幅に緩和され、オンライン授業中心の大学も可能になっている。この種の規制緩和がいっそう進むという予測からの想定であるが、2050年には主要な大学が全国各地の高校等の空教室を活用してサテライト・キャンパス(分校)を開設し、学生は自宅でのオンライン授業とサテライト・キャンパスでの対面授業で単位を取得して卒業できる形態が定着していると想像している。
サテライト・キャンパス化が進むと、入学定員の厳しい枠も不要となり、今日のような大学入試は、ごく一部の倍率の激しい有名大学にだけ残ることになる。
ということで、「探究」を内実化するうえで、阻害要因として大きかった入試システムは、それほど重要視する必要がなくなる、ということになる。
(学習院大学名誉教授 諏訪哲郎)